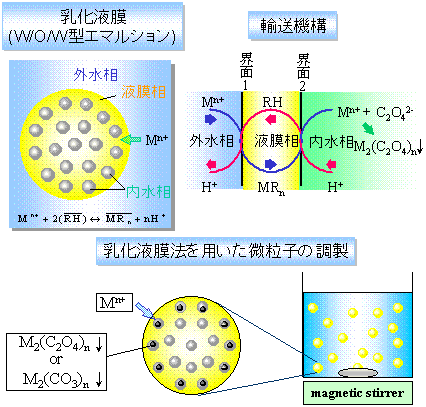|
研究概要 |
|
環境光工学グループ(平井研究室) |
太陽エネルギー・光エネルギーの有効利用による持続可能な社会の実現を目指して、下記のような研究を展開しています。
界面活性剤の自己集合により形成されるナノメータースケールの会合コロイド(逆ミセル)を微小反応場とするナノ超微粒子の調製と、調製したナノ粒子のプロセシング・材料化技術に関する研究を進めています。ナノメータースケールまで微細化された半導体粒子は、量子サイズ効果が発現し、バルク半導体では見られない新たな電子的・光学的特性を示します。これらのナノ粒子を利用して調製したナノ粒子−ポリマー、ナノ粒子−シリカなどの複合機能材料が水の光分解による水素エネルギーの製造のための光触媒や蛍光体として優れた機能を発現することを見いだしており、さらに新規なプロセシング技術の開発と機能材料の創製を目指しています。
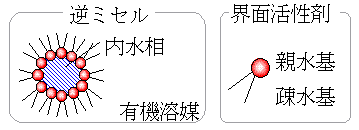
外水相・液膜相・ミクロンスケールの内水相から形成されるW/O/W型エマルションを反応場とし、ナノ〜サブミクロンサイズの微粒子材料の調製を行っています。反応物質の輸送・供給過程を制御することにより、微粒子の粒径や形態・結晶構造などを精密に制御することができます。各種の金属酸化物材料の前駆体として有用な金属しゅう酸塩や炭酸塩微粒子の調製をはじめ、希土類酸化物などの新規な光機能性微粒子および薄膜材料の開発に取り組んでいます。